第6話 蜜蜂 ■ 内藤更紗
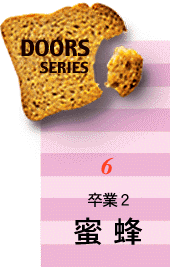 |
久しぶりの春雨だ。 銀色の細かな針をコートの肩に受けながら、おれは早足で家路に向かう。 年度末の繁忙期から抜け出して、やっと仕事が暇になった。 片手にはスーパーの袋が揺れている。 煮物の味を確かめてから、サラダの下ごしらえをする。 ピカピカに磨いたグラスに、あいつの好きな酒。 …遅いな。 せっかく気合いを入れて用意したのに。 待ちくたびれたおれは、読みかけの雑誌を投げ出してベッドにもぐり込む。 春の雨は音もない。 時折窓の外で、濡れた路面をタイヤがゆっくりと走り抜けていく。 「ユウ」 耳もとにあたたかい息がかかる。 「ユウ…、寝てるのか?」 うなじに髭があたってくすぐったい。 引き締まった腕がおれの上着のすそをたくしあげ、 なまの指がシャツの中に入ってくる。 脇からへそ、盲腸の手術痕、みぞおちのほくろ、乳首。 太い指の腹がそっとおれの乳首を押さえ、ゆっくりとこねる。 …ああ。 暗く深い壺の中で、まどろんでいた芯がピクンとはねる。 (どしたん?タツヤ、さっきから鼻くんくんさせてさ) (おまえ、レンゲの匂いするよ) (レンゲ?)おれは自分の匂いをかいでみる。 (わかんないけど…) (自分じゃわからないさ。でも、おれは) (何?) (おれは、その匂いだけで勃っちまう) おれだって、と言いかけて、ユウは言葉を飲み込んだ。 それはあんまり恥ずかしいし… タツヤの指が、おれの下腹部へと降りてくる。 ジーパンの上から内股をさすり、 膨らみの輪郭を探るようにすうっと指でなぞる。 思わず腰をうかせたおれを がっちりと両腕で抱き込んで、彼はおれの下半身をむいた。 「ユウ…」 脚と脚が絡められて腰から下は身動きがとれない。 尻に熱いものが押しつけられる。 狭い谷間を押し開くように濡れたものがこすられる。 握られた指の間から、おれの雄しべが屹立している。 匂いがする。おれの大好きなタツヤのあの匂い。 おれの雄しべから蜜が流れる。 タツヤの指が蜜をすくいとり、おれの谷間へ運び込む。 太く長いタツヤの針が、ずぶりと真芯に射し込まれた。 …ああ。 蜜壺がかきまぜられる。 蜜がストローで吸われていく。 内臓がシェイクのようにずるずると管を通って吸い出されていく気持ち良さ。 もっと、もっと、もっと奧まで刺して。 おれの全部を吸って。 からっぽになるまで、おれを吸って。 おれはからっぽになって、透明になって、雲を抜け、空を抜けて… ああ、今、雲の上だ、 雲の上で揺さぶられている、からっぽのおれ… 「ユウッ!」 突然、ものすごい力でおれの腰が後ろに引き戻され、 ぐっと刺された太い針の先から熱いジュースが管の内壁に浴びせられた。 おれは声をあげてシーツを握りしめ、両脚をぶるぶる突っ張らせて 開いた雄しべの先端から真っ白な蜜を飛ばした。 ・・・・・・・・・・ カチャカチャ、カチャカチャカチャ。 どこかで、キーを叩く軽快な音がする。 「やあ」 パソコンに向かっていたタツヤが、 ロフト・ベッドの上のおれに笑いかけた。 「……」 おれはなんとなくもじもじして、 丸まった布団から亀みたいに首だけ出して彼を見下ろす。 こんな時どう言えばいいのかわからない。 タツヤはパソコンのスイッチを切ると、 ベッドの上に上がってきた。 「ユウ、おまえさ」 「……」 「起きてたんだろ?最初から」 「…何のこと」 「だから、さっき」 「ワカンナイ、ネテタモン、ずっと」 「ふうん…」 タツヤはそう言うなり、急に布団の中に手を突っ込んで、おれの股間を握った。 「何すんだよ!」 「やろうよ、ユウちゃん」 「やだ!そんな何回も」 「やっぱり覚えてるんじゃないか。声だってあんなに…」 その続きは飛んできた枕にかき消された。 「バカ!」 その夜はさすがにそれ以上の気はおきなかった。 翌日もお互いに仕事なので、おとなしくベッドに入る。 「おまえ、今日早く帰れたということは、もう繁忙期終わったのか?」 「うん、整理がまだちょっと残ってるけどね」 「そうか。おれは明日からまた当分研究所泊りだ」 「え?」 「…それでしばらくおまえの顔見られないと思うと、つい、その…」 「……」 「ゴメンナ」 謝んなよ…。 おれは布団の中でタツヤの手を握る。 「電話するから」 「……」 「メールも入れるから、淋しくないよな?」 「ハイ、タッチャンハガンバリマス」 おれはタツヤの上に乗りかかって、ご褒美のキスをしてやる。 「あ」 「何?」 「ユウ、おまえさ…やっぱりレンゲの匂いがする」 「…じゃ、しばらく、こうしてよか?」 おれはタツヤの身体に体重をあずける。 「おれの匂い、忘れないように」 「…勃っちまうよ」 「もう無理だろ」 「チクショー、匂いがもったいない」 「何言ってんだよ」 「くそぉ、ユウ、浮気すんなよ、おまえはおれのもんだぞ」 「いいからもう寝ろよ」 タツヤがおれの背中に腕をまわす。 タツヤの匂いがおれを包む。 おれは目を閉じた。 音もない春雨の夜、おれたちはお互いの鼓動を聞きながら眠りに落ちた。 |
第6話 蜜蜂 了
●TOPに戻る ●第7話を読む